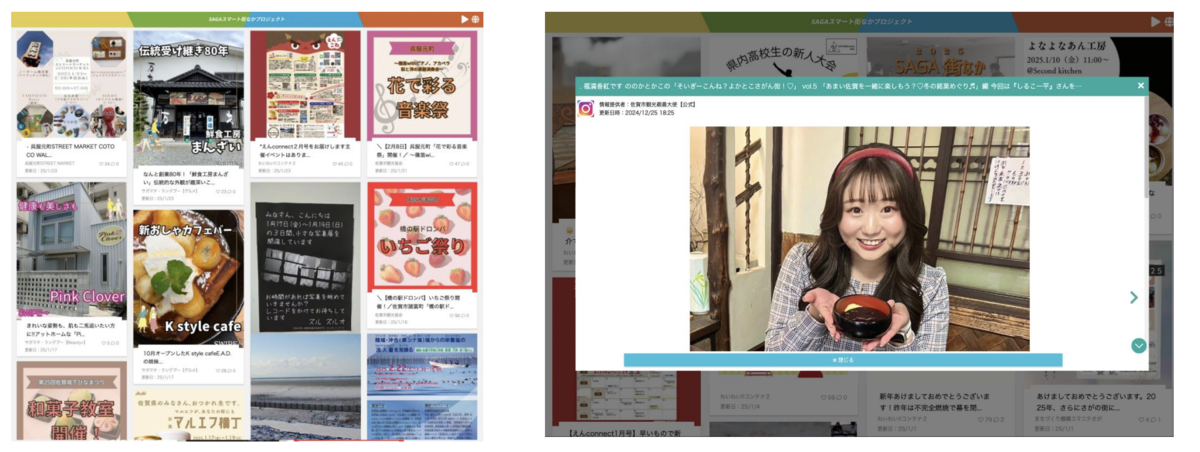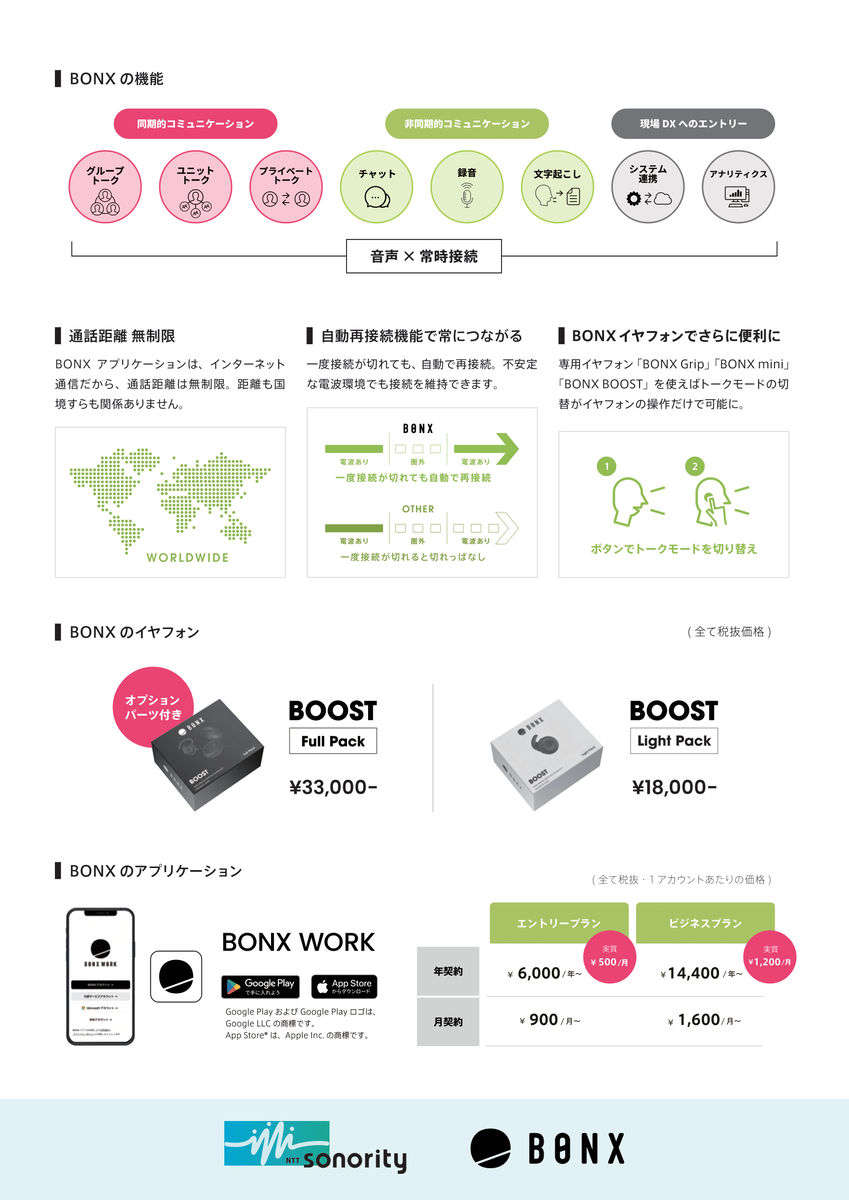当社(ウェブインパクト)では、地域の課題解決に直結する実践型インターンシップを積極的に行っています。大学生や留学生など、さまざまなバックグラウンドを持つ方々が参加し、現場での体験を通じて、デジタル技術を活用した地域課題の解決に取り組んでいます。
今回は、愛知工科大学の学生と東フィンランド大学からの海外留学生による、実際のインターン事例をダイジェストでご紹介します。学生たちの挑戦と成長の様子を、ぜひご覧ください。
【愛知工科大学】駐車場オープンデータと地図アプリ開発
愛知工科大学の学生によるインターンでは、豊橋市の駐車場情報を活用したオープンデータプロジェクトに取り組んでいただきました。
このプロジェクトでは、豊橋市まちなか周辺に点在する駐車場の情報を収集・整理したうえで、誰もが利用できるオープンデータとして公開できるようにデータを作成。さらに、「どすごいマップ(https://www.dsmap.net/)」というノーコードで地図アプリを作成できるサービスを活用し、駐車場情報をわかりやすく地図上で確認できる「豊橋駐車場マップ」アプリの開発も行いました。

情報収集からデータ整理、運用のためのワークフロー構築、登録・更新用フォームの作成など、現場で求められる一連のプロセスを学生自らが担当して構築。さらに、収集データのメンテナンスや運用方法についてもマニュアルとしてまとめていただき、今後の地域の情報発信に役立つ仕組みづくりに貢献して頂きました。
インターンを通じて、実際の地域課題に向き合いながら、データ活用やアプリ開発の実務経験を積んでいただきました。こうした体験が学生の成長や地域への新たな価値提供につながることを、当社としても大変嬉しく思います。
詳細は以下の記事をご覧ください。
【東フィンランド大学】AR手筒花火アプリの開発
東フィンランド大学から留学生としてきた大学院生が、3か月間にわたり地域の伝統文化をデジタル技術で体験できるアプリ開発に取り組みました。

豊橋の伝統行事である手筒花火をテーマに、スマートフォンのブラウザ上でAR(拡張現実)体験ができるアプリを開発。ARマーカーを認識し、現実の動きに合わせて花火の映像や音を再現するなど、プログラミングやデザインの新しいスキルを実践の中で磨いていただきました。

異なる文化や視点を持つ留学生が、地域の魅力を発信する技術開発にチャレンジしたことで、当社にとっても多くの学びと刺激を得る機会となりました。
詳細は以下の記事をご覧ください。
地域課題に取り組む、実践型インターン
今回は当社インターンシップにおける地域課題をテーマにした実践型プロジェクトに取り組んで頂いた事例をご紹介いたしました。学生や留学生が自ら考え、現場で手を動かす経験を通じて、社会に役立つサービスや仕組みづくりに取り組んでもらうことで、ITスキルだけでなく、課題解決力やチームワークも自然と身につくと考えています。
当社では、今後も地域に貢献できるインターンの場を提供してまいります。興味のある方は、ぜひ当社インターンへのご応募をご検討ください。
ウェブインパクトで共に働きませんか?エンジニア募集!